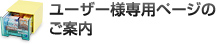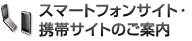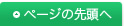配置薬の歴史
配置薬は日本人の独創

配置薬の祖、富山藩第2代藩主・前田正甫(まさとし)公の像。
配置薬業の歴史は約300年。
富山藩第2代藩主・前田正甫(まえだまさとし)公が、江戸城内で腹痛に苦しむ三春藩(福島県)の藩主・秋田河内守(あきたかわちのかみ)に、『反魂丹(はんごんたん)』という妙薬を与えたところ、腹痛が治りました。
その場に居合わせた諸国の大名が、ぜひ自分の領内でも売り広めて欲しいと依頼した事が、配置薬の発祥とされています。
顧客本位の「先用後利」

「懸場帳(かけばちょう)」。得意先が使用した薬などが記載された、いわば顧客データベース。

ニュースの運び手でもあった売薬行商人。
富山の売薬行商人が秘伝の丸薬を諸国に売り歩いたのが起源とされています。各々の得意先台帳を元に半年から一年ごとに訪ねてくる売薬行商人は医療体制が整っていなかった時代に庶民にとって頼もしい存在であったに違いありません。
また今日のようにメディアの無い時代ですから、諸国を旅する売薬行商人は、庶民にとって貴重なニュースの運び手でもありました。彼等売薬行商人たちの最大の特徴は「先用後利」という信用取引です。代金の支払い無しに常備薬を預け、半年・一年後に使った分だけ清算し新たな薬を補充するという顧客本位の画期的な販売法は絶大な支持を得ました。顧客と薬売り人の関係は何代も続いて親戚同然のお付き合いが維持されていました。
薬売りの伝統は近代に入っても引き継がれ、明治・大正・昭和・平成と活躍してきました。「先用後利」は顧客優先の先駆的思想においても歴史の長さにおいても世界に例の無いものです。そして現在の配置薬業は医薬品とともに健康関連商品をも総合的に供給するシステムとしてさらに発展しようとしています。

「柳行李(やなぎごうり)」。この中にくすりや紙風船などを入れ、行商していた。

「用を先にし、利を後にする」先用後利の商法。

各家庭で利用されていた「薬箱」。